犬の口臭の原因について解説!原因とケア方法まとめ

犬の口臭が気になる場合、口の中や体内で何かしらトラブルが起こっていることが考えられます。犬でも人間でも多少は口のニオイがするものですので、必ずしも心配すべきトラブルばかりではありません。
しかし、いつもとは明らかに違うニオイ、強烈なニオイがする時は注意が必要です。
本記事では、犬の口臭の症状や原因、オススメな対策について徹底解説します。犬の健康を守るためにも、ぜひ参考にしてみてください。
犬の口が臭い原因とは?

犬の口が臭いと一言で言っても、その臭さによって原因が異なります。生臭いような魚臭いようなニオイがすることもあれば、酸っぱいようなアンモニア臭に近いニオイがするケースも少なくありません。
一般的には、歯磨きをちゃんとできていないため、食べかすなどが溜まって口の中が不潔な状態になっているケースが比較的多いです。いずれせよ対策を考える前に、まず、原因別に詳しい状態をチェックしておきましょう。
犬の口臭が魚臭いケース
通常、犬の口の中には適度な量の唾液が溜まっています。そのおかげで口の中が適度に潤っているのですが、何らかの原因で口の中の水分が少なくなると、唾液が濃縮され粘っこくなることがあります。この時、魚っぽい生臭さを感じることが多いです。
口の中の水分が少なくなるのは、単に飲む水の量が少なくなっているだけでなく、鼻づまりや鼻炎の影響で犬が口を常に開けた状態で過ごしていることが考えられます。
犬が口を開けてハアハア呼吸する姿は珍しくありません。健康な犬でも、特に運動後や暑い時期は、体温調節のために口呼吸を行います。ただ、そういう時はいつもより口の中が乾燥しやすくなっていることに注意しましょう。
犬の口臭が酸っぱいケース
犬の口から酸っぱいニオイがする時は胃腸・肝臓・腎臓などの不調が疑われます。人間でも胃腸に不調がある時には口臭が酸っぱくなりますが、犬も胃炎によって胃酸が分泌過多になります。
胃酸が逆流してきたり嘔吐してしまったりすることがあり、胃酸の酸っぱさが口臭となって表れます。胃炎を起こす原因はさまざまですが、単に長く空腹でいることから、中毒や感染症、また、ある病気の二次症状というふうにさまざまです。
また、同じく酸っぱいニオイでもアンモニア臭がする時は、肝臓や腎臓の不調を疑いましょう。これらの臓器が正常に機能していないと、体の外へ通常なら排出される不要物が体内に溜まって、アンモニア臭のような独特のニオイを発生させることがあるのです。
便臭がする場合は注意
内臓に由来する口臭で言うと、犬の口から便臭がする時は注意してください。ひどい便秘や腸捻転や腸閉塞を起こしている可能性が考えられます。
これらの症状は、異物の飲み込み、内臓の腫瘍、重積がおもな原因です。正常に腸の内容物が排出されず、口の方に逆流してくるため、便のようなニオイがします。
まれに便に近い吐瀉物を吐くこともあるようです。嘔吐するような場合、かなり深刻な症状が疑われますから、早急に動物病院で診てもらいましょう。
食べかすなどが由来の腐敗臭がするケース

犬の口から腐敗臭がする場合、ふだん食べているドッグフードに問題があることがあります。開封するとドッグフードは空気に触れ酸化が進行していき、フードの品質が劣化していくことに注意が必要です。質の劣化したフードは腹痛、下痢、嘔吐などの原因です。開封後はきちんと封をして冷暗所で保管し、賞味期限内になるべく早く食べるようにしましょう。
また、歯周病によっても口臭が腐ったようなニオイになります。犬は歯周病になりやすい動物ですので注意が必要です。人間よりも歯垢が歯石になるまでの期間が短いため、比較的気をつけているつもりでも一定以上の年齢になると歯周病になってしまうことがあります。
歯周病を予防するには、毎日の丁寧な歯磨きが欠かせません。犬は自分で歯磨きできないので、犬の歯周病の原因は飼い主にあると考え、ちゃんとケアしてあげましょう。
愛犬の口臭予防・改善のためにできること

今述べたように、愛犬の口臭対策として飼い主がまずできることは歯磨きです。口の中に食べかすが溜まることで、それが歯垢や歯石になり、歯周病を発症させてしまいます。その原因である食べかすを残さないように、飼い主は正しい歯磨きの方法を覚えて、毎日の習慣にしましょう。正しい歯磨きの方法は動物病院などで教えてもらえます。
ただし、これまで歯磨きをしたことのない犬の場合、大人になってから習慣にしようと思っても、なかなか思いどおりに磨かせてくれないでしょう。
その場合は『歯垢トルトル ボーダン 』がおすすめです。
『歯垢トルトル ボーダン 』は、歯の隙間の細かい汚れを電解水が取り除きます。
また、PH12のミネラル電解水ですのでもちろん完全無添加です。ご使用方法は、飲み水100mlにつき1プッシュするのみです。商品は、約4ヶ月間程持ちますので、お財布にも優しいです。
歯ブラシが苦手な子は、歯垢トルトル ボーダンを是非使用頂き、歯のケアを行ってあげましょう!
愛犬とのスキンシップの一環として毎日の口臭ケアを
犬の口が臭いと感じた時は、まず原因を見極めるためによく観察しましょう。
日ごろから歯磨きなどのケアを習慣にしていると、何か異常があった時にもすぐに気づけます。スキンシップの一環としてぜひ毎日続けましょう。
ただし、異常な口臭は内臓などの病気に由来するケースもあります。「おかしいな」と思った時はなるべく早めに動物病院に連れていってあげてください。
また、溜まった歯石の除去もしてもらえるので、犬の口臭や口腔内のことで気になることがある時は動物病院で診てもらいましょう。
わんちゃんライフについて
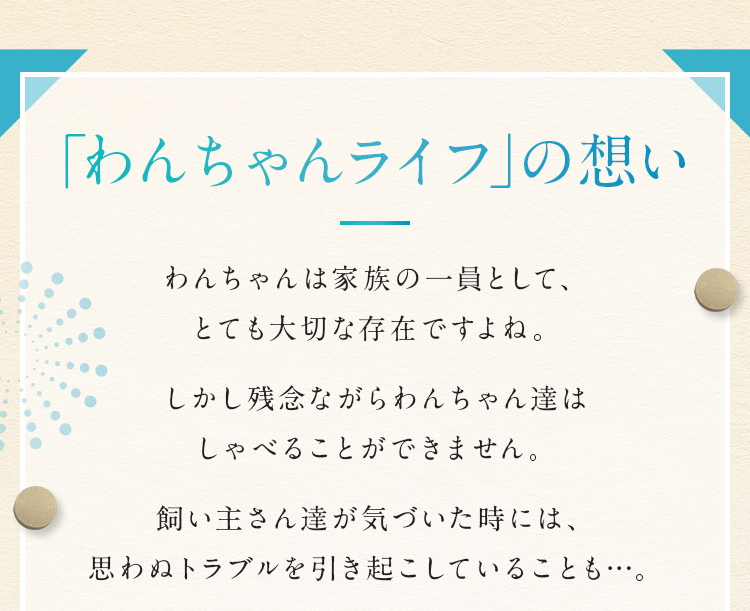
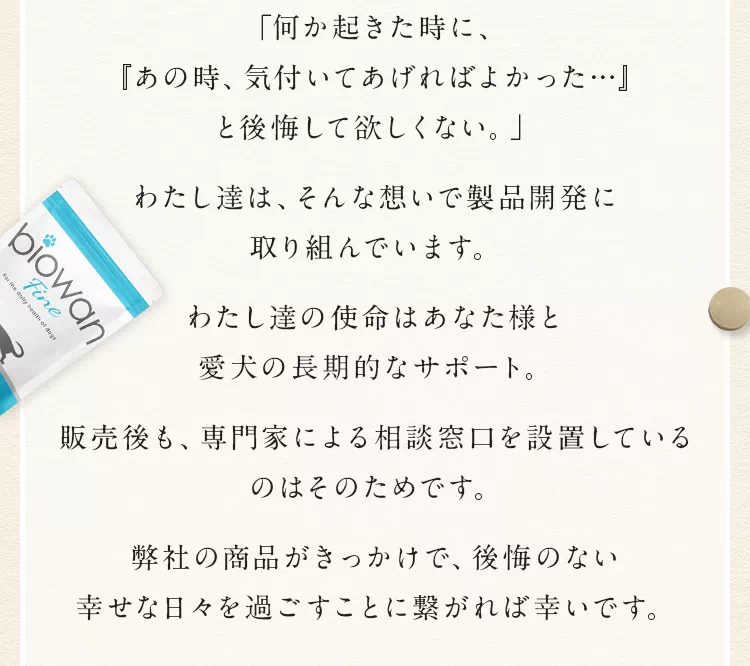


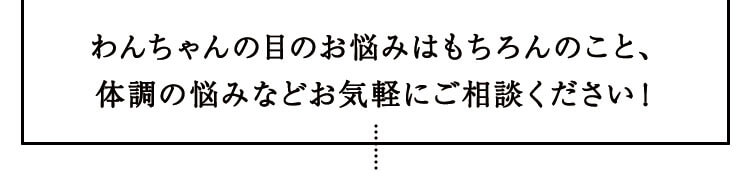

「わんちゃんライフ」では、HPよりドックフード・日用品・サプリメントなどの商品をお得に購入することができます。
500円OFFクーポンを公式ラインから取得し、ぜひご活用ください。
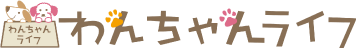



 ログイン
ログイン
 カート
カート
 お問い合わせ
お問い合わせ
 商品ラインナップ
商品ラインナップ
 カート
カート
 お問い合わせ
お問い合わせ

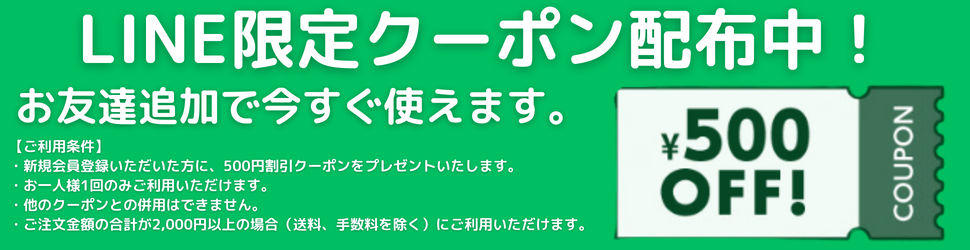
 ラインナップはこちらから
ラインナップはこちらから お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら