愛犬の痙攣とは?病院に連れていくべき症状やタイミングとは?

突然、体を硬直させピクピク動く愛犬の姿に驚く人もいると思います。犬の痙攣は何の前触れもなく突然起こる可能性があるため、適切な対処法を理解しておく必要があります。
この記事では、犬の痙攣で起こる症状や原因をはじめ、動物病院を受診する目安や痙攣が起きたときの対処法などについてご紹介します。いざというときに冷静な対応ができるよう、犬の痙攣についての知識を身につけておきましょう。
犬の痙攣とは?

犬の痙攣とは、犬の意志とは関係なく全身の筋肉が震えるように動いてしまうこと。体に指令をだす脳の一部が一時的に異常を起こし、痙攣してしまいます。犬に痙攣が起こると、以下のような症状がみられます。
・体の一部(全身の場合も)を硬直させて震える
・体の一部がピクピクと一定のリズムで動く
・倒れて足をバタバタさせる
・よだれが大量にでる
・嘔吐する
・失禁する
・意識が朦朧とする(意識がなくなる)
・呼吸が何秒か止まる など
痙攣の症状は明らかに普段と様子が違うため、すぐに分かります。
犬の痙攣の原因
では、犬が痙攣を起こす原因にはどのような要因があるのでしょうか?ここでは、犬の痙攣の原因を解説します。
筋肉の疲れ
犬は激しい運動をすると筋肉が疲れ、ピクピクと痙攣のような動きをすることがあります。筋肉疲労による痙攣は生理現象のようなものなので、それほど心配する必要はありません。
寝ているときに足や手がピクピク動いたり、バタバタしたりするのも夢をみている可能性が高いので、それほど心配はないでしょう。
病気の可能性もある
気がつかないうちになにかしらの病気にかかり、その病気の症状の1つとして痙攣が起こる可能性も考えられます。以下は痙攣が起こる可能性のある病気です。
・てんかん
・食中毒
・慢性腎不全
・熱中症
・水頭症
ここでは、それぞれの病気についてより詳しくご紹介します。
てんかん
てんかんとは、脳の神経細胞が過剰に興奮することによって起こる発作。一時的な脳の機能障害で、てんかん発作の代表的な症状は痙攣です。
てんかんには、「特発性てんかん」と「症候性てんかん」の2種類があり、特発性てんかんは何の前触れもなく突然起こります。また、原因は明らかにされていなく、遺伝的な要素が強いようです。
比較的若い犬に多く発症しやすく、生涯一度きりしか起こらない犬もいれば、定期的に発作を起こす犬もいます。一般的にてんかんと呼ばれるのは、特発性てんかんです。
一方、症候性てんかんは、病気や怪我が原因となり引き起こされるてんかんです。一般的に突発性てんかんより症状が重く、最悪の場合は死に至る可能性もあります。
食中毒

食中毒とは、有害な食べ物を犬が摂取し、ウイルスや細菌などにより体に不調が表れる病気です。食中毒の主な症状は以下の通りです。
・下痢
・嘔吐
・腹痛
・発熱 など
重症の場合は痙攣や麻痺を起こす場合があります。例えば、殺虫剤などの害虫駆除液を口にしてしまった場合、痙攣を起こすことがあるでしょう。
慢性腎不全
痙攣の原因5つ目は、慢性腎不全です。慢性腎不全とは、腎臓が正常に機能しないことにより体に不調をきたす病気のこと。腎臓が正常に機能しないと、本来、体から排出されるはずの尿が体内にたまってしまいます。その結果、痙攣や震えが起きます。
慢性腎不全になってしまうと、痙攣の他に、筋力の低下や体の痛みなどの症状が表れます。慢性腎不全は数カ月から数十年かけて徐々に腎機能が低下していくため、痙攣を起こしたことにより、初めて慢性腎不全に気付くケースもあります。
熱中症
熱中症とは、体温の上昇による脱水症状が体に不調をきたす病気のこと。主な症状は以下の通りです。
・呼吸が荒い
・心拍数が高い
・よだれが多い
・ぐったりして元気がない
・落ち着きがない など
重症になると、痙攣を引き起こす可能性もあります。
水頭症
水頭症では、脳の中にある脳室に脳脊髄液が正常量以上にたまってしまい、主に以下の症状が表れます。
・痙攣
・食欲がなくなる
・ぐったりして元気がない
・寝てばかりいる
・視力障害が起こる など
犬を病院に連れていくべき症状・タイミング

愛犬が突然痙攣を起こした場合「急いで病院に行かなければ」と思う人もいるかもしれません。しかし、症状によっては自宅で様子を見るだけで問題ない場合があります。
・痙攣後、すぐに回復して普段と様子が変わらない場合
・睡眠時のピクピク動く痙攣の場合
・寒さによる震えの場合 など
上記のケースは、重篤な病気が潜んでいる可能性は低いので、そこまで心配する必要はないでしょう。
逆に、動物病院を受診した方がいい症状やタイミングは以下の通りです。
・痙攣が長く続く場合
・一日に何度も痙攣を起こしている場合
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
痙攣が長く続く場合
痙攣が3分以上と長く続いている場合は、動物病院で診てもらった方が良いかもしれません。犬の痙攣は一般的には3分以内で治まることが多いため、3分以上続いた場合は要注意です。
本来であれば、痙攣が落ち着いてから受診した方が良いですが、なかなか収まらない場合は痙攣が起きている状態でも病院に連れていきましょう。痙攣している犬を動かす際には、飼い主さんにも犬にも怪我がないよう、慎重に行動してください。
他にも、明らかに呼吸をしていない、意識がない場合なども緊急性が高いため、早めの受診が大切です。
一日に何度も痙攣を起こしている場合
1日に何度も痙攣を起こしている場合も受診をおすすめします。また、犬の意識がはっきりしないうちに次の痙攣を起こした場合も、緊急性は高いでしょう。
これらの症状が長引くと、脳へのダメージが大きくなってしまいます。痙攣が起きている状態でも、動物病院に連れていきましょう。
犬が痙攣を起こした場合の対処方法

最後に、犬が痙攣を起こした場合の対処法をご紹介します。愛犬が痙攣を起こした時、普段と違う姿に慌ててしまいがちですが、落ち着いて適切に対処することが大切です。
犬の安全を確保する
痙攣は犬の意志に関係なく体が動いてしまうため、普段過ごしている場所でも、犬が怪我をしてしまう可能性があります。以下のポイントを考慮しながら、まずは愛犬の安全を確保してあげましょう。
・周囲にぶつかりそうな物があれば片付ける
・階段が近くにある場合は、落ちないように工夫する
・犬の周囲をクッション性のある物で囲ってあげる
また、散歩中など外出先で痙攣が起きた場合は、犬のおしりを支えながら安全な場所まで移動させてあげましょう。
痙攣中は触らずに状況を記録する
犬が痙攣を起こすとつい心配で体を触ってしまいがちですが、お互いの安全のため、基本的には触らずに見守ることが重要です。その際、後から獣医さんに相談しやすいよう、愛犬の症状を記録しておきましょう。
・痙攣の継続時間
・痙攣を起こす前の犬の様子
・痙攣している部位、よだれや嘔吐の有無など、痙攣中の犬の症状
上記のポイントを獣医さんに伝えると、より正確に診断しやすくなります。また、動画を撮っておくのもおすすめです。
一方、以下の行動は症状を悪化させてしまう可能性があるため、行わないようにしましょう。
・痙攣を起こしている犬を無理やりおさえつける
・犬の体を揺らす・起こす
・必要以上に大きな声で名前を呼ぶ
・犬の口にタオルを挟む
回復したら様子を見る
痙攣が終わり、ある程度愛犬の回復が確認できたら、痙攣前と違った様子はないか確認しましょう。また、首輪をつけている場合は外してラクにしてあげるのがおすすめです。
嘔吐物やよだれなどがついている場合は拭いてあげてください。愛犬を触っても問題ないようなら、体に触れて、怪我や痛がっている場所はないかを確認することも大切です。痙攣から1週間程度は、普段以上に愛犬の様子を気にかけてあげましょう。
必要に応じて動物病院を受診する
痙攣後、なにかしらの異変があったり、痙攣を起こす前と様子が違ったりする場合は、動物病院を受診しましょう。加えて、先ほどご紹介した症状がある場合も、診てもらうことが大切です。
犬は飼い主の気持ちがわかる生き物のため、飼い主が不安だと犬も不安になってしまう可能性があります。特に異常がない場合でも、受診することで安心できるなら、迷わずに受診しましょう。
まとめ
犬が痙攣を起こす原因はさまざまなので、痙攣を予防する得策はありません。しかし、痙攣の原因を大きく分けると、筋肉疲労と病気になるため、食事改善で予防できる可能性があります。
そこでおすすめしたいのが、犬の健康維持を目的としたサプリ「カームワン」です。カームワンに含まれる以下の成分には、脳神経機能や肝機能を整える効果があるため、痙攣をよく起こすワンちゃんにも最適です。
粉末タイプのサプリなので、普段のフードにふりかけるだけで必要な栄養補給が可能。犬が大好きなチキン風味のため、そのままおやつとしても楽しめます。犬の管理栄養士が全面監修して作られたカームワンを、この機会にぜひ試してみてください。
わんちゃんライフについて
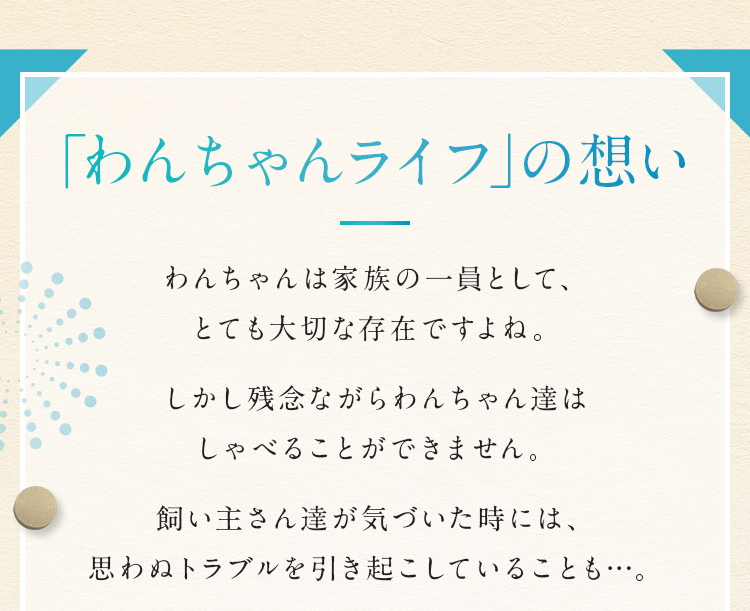
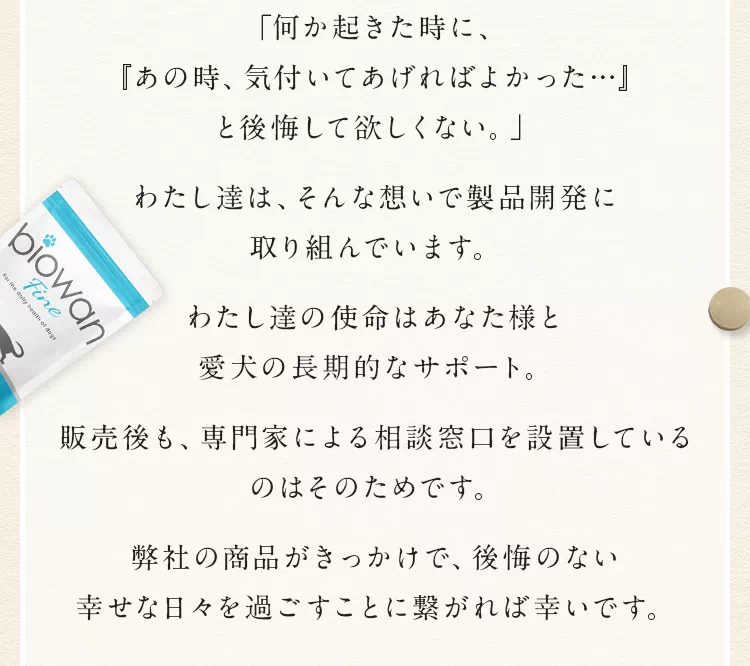


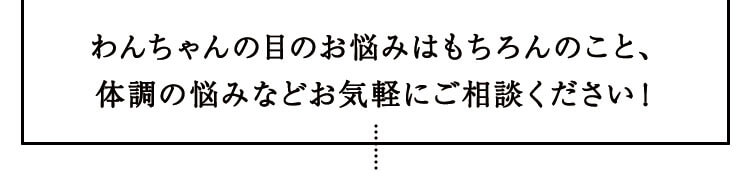

「わんちゃんライフ」では、HPよりドックフード・日用品・サプリメントなどの商品をお得に購入することができます。
500円OFFクーポンを公式ラインから取得し、ぜひご活用ください。
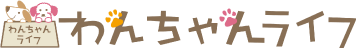



 ログイン
ログイン
 カート
カート
 お問い合わせ
お問い合わせ
 商品ラインナップ
商品ラインナップ
 カート
カート
 お問い合わせ
お問い合わせ

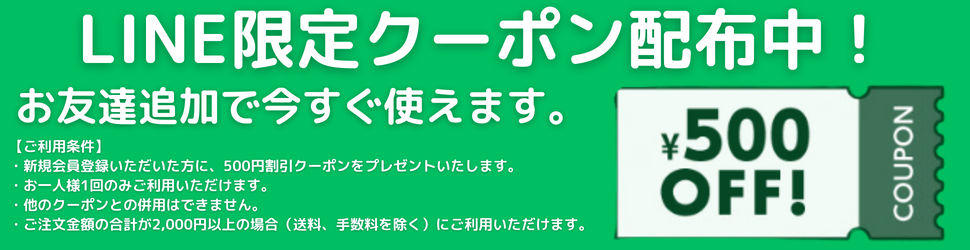
 ラインナップはこちらから
ラインナップはこちらから お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら