犬の膵炎は食事管理が重要!食べていいもの、いけないものとは?

犬が膵炎にかかった場合、食事を徹底的に管理することが求められます。治療中に食べさせていいものといけないものがあるため、愛犬が膵炎と診断されたら、飼い主による食事のコントロールが必要です。
本記事では、食事管理の重要性、治療中に控えたい・取り入れたい栄養素、食事管理のポイントなどを解説します。ドッグフードと手作り食のメリット・デメリットについても触れているので、膵炎の治療だけでなく愛犬の食事管理について理解を深めたい人はぜひ参考にしてみてください。
食事管理の重要性

犬の膵炎は食事管理が重要です。そもそも膵炎とは、膵臓で炎症が起きる病気のこと。膵臓は食べ物の消化に必要な消化酵素を生成し、分泌するための臓器です。膵臓が正常に働いているときは、消化酵素が膵臓を消化しないように不活性の状態で分泌されるため、膵臓自体が消化される心配はありません。
しかし、何らかの原因によって膵臓が正常に機能しなくなると、活性化した消化酵素が膵臓を消化し炎症を起こします。膵炎の症状には次のようなものがあります。
・食欲低下
・発熱
・よだれ
・脱水
・黄疸
・震え
・衰弱
・腹痛
・下痢、軟便、血便
・嘔吐
・呼吸困難
・ショック
・多臓器不全 など
犬の膵炎の原因は明確ではありませんが、脂肪の摂りすぎや栄養が偏った食生活や肥満などに関係があるのではないかと考えられています。そのため、犬の膵炎は脂質をはじめとした食事管理が重要です。
治療中に控えたい栄養素
では、愛犬に食事を与える際にはどのような点に注意すれば良いのでしょうか。
膵炎の治療中は、控えた方が良いとされている栄養素があります。それは「脂肪」と「糖質」です。ここでは、いずれもの栄養素を避けるべき理由について詳しく解説します。
脂肪
脂肪とは三大栄養素の一つで、水に溶けない性質を持ち、エネルギー源として体内で使われます。過剰摂取により余ってしまった脂肪は体内に蓄積し、肥満に繋がる可能性があります。そのため、摂取量のコントロールが欠かせません。
脂肪の摂取量を管理するためにも、下記のポイントに注意することが大切です。
・「低脂肪」の食事を与える
・酸化した脂肪は避ける
・オメガ3脂肪酸などの良質な脂肪を摂取させる
「低脂肪」の食事を与える
脂肪が多い食事は、脂肪を消化するために膵臓から多くの消化酵素が分泌され、膵炎の進行を早めてしまうリスクがあります。低脂肪の食事にすれば、膵臓で分泌される消化酵素を抑えることが可能です。
ただし、脂肪をゼロにすれば良いという訳ではありません。脂肪は犬の体に必要な三大栄養素の一つ。脂肪を一切摂らなくなると、体の機能や筋肉などを働かせるためのエネルギーが不足してしまいます。脂肪は糖質やタンパク質と比べて2倍以上のカロリーがあるため、エネルギー源として欠かせません。だからこそ、膵炎には脂肪の量を抑えてくれる「低脂肪」が最適だと言われています。
酸化した脂肪は避ける
犬の膵炎の治療中には、酸化した脂肪を与えないようにしましょう。酸化した脂肪は金属のサビと同じで、犬の体にとって毒です。体内に酸化した脂肪が取り込まれると、大きな負担がかかる恐れがあります。脂肪が酸化しやすい食べ物とは、例えば酸化が進んだドッグフードや高温で加熱・乾燥させたジャーキーなどです。
未開封のドッグフードであれば、袋が密閉されているため酸化することはほぼありません。しかし、開封してから数ヶ月経っているドッグフードなどは注意が必要。短期間で食べ切れるサイズのドッグフードを購入することをおすすめします。
オメガ3脂肪酸などの良質な脂肪がおすすめ
犬にとって良いとされている脂肪は、「オメガ3脂肪酸」などの良質な脂肪ですオメガ3脂肪酸は、摂取しても、膵臓の消化酵素の分泌を促進させない特徴があります。
また、こちらの脂肪は人の膵臓の炎症を抑える働きを持っていることが明らかになっています。人間の膵炎に効果があるとされていることから、犬の膵炎にも同様の効果が得られるのではと期待されています。
オメガ3脂肪酸が含まれている食品は、キャノーラ油やココナッツ油、ヒマワリ油、アマニ油、サーモン油などです。
糖質
糖質は、三大栄養素の一つである炭水化物に含まれる栄養素です。炭水化物とは、糖質と食物繊維を合わせたもの。エネルギー源に利用できるカロリーは脂肪よりも半分以下ですが、効率よくエネルギーを作ることができるため、犬の食事に欠かせません。
ただし、犬が膵炎と糖尿病を併発した場合は、糖質を制限する必要があります。以下では、糖質の摂取について詳しく解説します。
消化の良い糖質はなるべく排除する
膵炎にかかった犬が糖尿病を併発した場合は、低脂肪の食事にするだけでなく、消化の良い糖質はなるべく排除することが大切です。そうしなければ、急激に血糖値が上がってしまう可能性があります。血糖値の上昇は、糖尿病の症状を悪化させる恐れがあります。
消化の良い糖質とは、例えばブドウ糖や砂糖などです。精白された白米や食パンなどに含まれている可能性があるので、注意しましょう。
消化の悪い糖質を適量に与える
糖尿病を併発した膵炎の犬であっても、糖質を完全に排除することが良い訳ではありません。脂肪と同じように、犬の体にとって適度な糖質は欠かせないもの。そのため、消化しづらい糖質を適量に与えることが大切です。
消化の悪い糖質であれば、血糖値が緩やかに上昇するため、糖尿病の症状が悪化するのを未然に防ぐことができます。
消化の悪い糖質には、オリゴ糖や食物繊維などがあります。オリゴ糖はブドウ糖と同じ糖類の一つですが、オリゴ糖はエネルギー源として利用されず、腸内で分解・吸収されます。整腸作用がある一方、大量に摂取すると下痢を起こす可能性があるため、注意が必要です。
治療中に取り入れたい栄養素

それでは次に、犬の膵炎の治療中に取り入れたい栄養素について確認しておきましょう。膵炎の治療中に取り入れたい栄養素は、下記の通りです。
・タンパク質
・食物繊維
それぞれについて詳しくご紹介します。
タンパク質
タンパク質は、上述した脂肪や炭水化物と同じ三大栄養素の一つです。大きく分けて、肉・魚などに含まれる「動物性」と穀類・豆類などに含まれる「植物性」の2種類があります。
タンパク質はエネルギー源として体内で利用されるだけでなく、臓器や筋肉、骨、皮膚、毛髪などを作る役割を担っています。また、体内で起こっている炎症を修復する働きもあるため、膵炎の治療中の食事に欠かせません。
良質なタンパク質がポイント
犬の膵炎の治療中は、良質なタンパク質を取り入れることが大切です。良質なタンパク質とは、高温で加熱されていない肉類などの消化しやすいタンパク質を指します。
消化の良いタンパク質が重要な理由は、膵臓で消化酵素の分泌を促進しないためです。消化しづらいタンパク質だと、一部のアミノ酸の働きにより膵臓が刺激され、消化酵素が分泌されやすくなってしまいます。一方、良質なタンパク質は腸内に留まる時間が短いので、膵臓への刺激を減らせます。
アミノ酸のバランスを重視する
犬の膵炎をケアするためには、アミノ酸のバランスを重視した食事が大切です。アミノ酸はタンパク質を構成する成分で、「必須アミノ酸」と「非必須アミノ酸」に分けられています。
非必須アミノ酸は体内で作り出せますが、必須アミノ酸は体内で作れないので、食べ物から摂取しなければなりません。犬の体内で作れない必須アミノ酸は、10種類あります。
・アルギニン
・ヒスチジン
・イソロイシン
・バリン
・ロイシン
・メチオニン
・スレオニン
・リジン
・トリプトファン
・フェニルアラニン
犬の膵炎の治療中は、上記のアミノ酸をバランス良く摂取することがとても大切。そこで参考にしてみたいのが、「アミノ酸スコア」です。アミノ酸スコアは、必須アミノ酸のバランスを評価したスコアで、最大値を100としています。
小麦加工食品は避ける
犬の膵炎の治療中は、小麦の加工食品を含まない食事を与えましょう。パンや麺類などの小麦を使用した加工食品は消化しづらいため、治療中の食事には向いていません。小麦には、タンパク質の一つである小麦グルテンが多く含まれています。小麦グルテンは粘りの強い性質を持つため、消化されにくい特徴があります。
消化されにくいタンパク質は腸内で長く滞留し、膵臓に刺激が与えられるため、注意が必要です。ドッグフードを買い替える場合は、新鮮で消化しやすいタンパク質を多く含んだものや、「グルテンフリー」「グレインフリー(穀物不使用)」などと記載された、膵臓や腸に負担がかかりにくいものを選ぶようにしましょう。
食物繊維
犬の膵炎の治療中は、食物繊維も適度に取り入れることが大切です。食物繊維は膵炎によって腸内にかかっている負担を減らし、腸内環境を改善するのに役立ちます。
食物繊維は腸内の善玉菌のエサとして、腸内の健康を保つ役割を担っている成分の一つ。善玉菌が増えて腸内環境が良くなると、腸と密接な関係がある免疫力の維持につながり、活性化した免疫細胞が血中の余分な脂肪やコレステロール、糖質などが分解されます。
血中の余分な脂肪や糖質が減れば、高脂血症・高血糖などの病気を併発するリスクを抑えられます。ただし、ゴボウなどの食物繊維を多く含む食品は消化不良を起こす恐れがあるため、控えた方が無難です。
犬が膵炎になった場合、ドッグフードと手作りのどっちが良い?
犬の膵炎の治療には適切な食事が欠かせません。それでは、愛犬が膵炎と診断された場合、ドッグフードと手作りのどちらを選べば良いのでしょうか。
ここでは、それぞれの特徴やメリット・デメリットを紹介します。ドッグフードの選び方や手作りご飯のコツも合わせて紹介するので、しっかり比較してみてください。
ドッグフード

ドッグフードには大きく分けて、水分含有量が少ない「ドライタイプ」と水分含有量が多い「ウェットタイプ」があります。愛犬の好みや食べやすさだけではなく、栄養バランスの良い総合栄養食のドッグフードを選びましょう。
ドッグフードのメリットとデメリット
ドッグフードのメリットには、次のようなものがあります。
・栄養のバランスが取れている
・食事の支度に時間がかからない
・未開封なら長期間保存できる
総合栄養食のドッグフードは、犬の体に必要な栄養を偏りなく摂取できます。ドライタイプのドッグフードなら、愛犬の年齢や体重に合った量をボウルに入れるだけなので、食事の支度に時間や手間がかかりません。また、未開封の場合は長期間保存できるため、非常用の愛犬の食事として保管しておくことも可能です。
一方で、次のようなデメリットがあります。
・ほとんどの場合オーダーメイドは不可
・味気のない食事の可能性がある
ドッグフードは基本的に、オーダーメイドに対応していません。また、フードが乾燥しているため、犬によっては味気がないと感じてしまう場合もあります。
ドッグフードを選ぶコツ
膵炎治療中の愛犬に合うドッグフードを選ぶコツは、以下のとおりです。
・低脂肪で、良質なタンパク質を使用している
・食物繊維・難消化性の炭水化物が含まれている
・グルテンフリー・グレインフリーの表記がある など
前述した通り、膵炎になった犬の食事には、「低脂肪」「消化しづらい糖質」「良質なタンパク質」「食物繊維」などの条件が欠かせません。そのため、ドッグフードを選ぶときも、上記を考慮することが大切です。
ドッグフードの原材料に何が使用されているのもしっかり確認したうえで選んでみましょう。
手作り食

犬のご飯には、自宅にある食材を使用してご飯を作ってあげる、手作りという選択肢もあります。
ここでは、膵炎にかかった犬の食事を手作りするメリット・デメリットや、手作り食を作る際のコツについて詳しくご紹介します。
手作りのメリットとデメリット
犬の食事を手作りするメリットは、次のようなものがあります。
・食材の鮮度や種類にこだわりを持てる
・愛犬の年齢や体重、体調に合わせて調整できる
・見た目が良く、素材の味を活かせる など
ご飯を手作りする場合は、愛犬の好きな食材や栄養素をたっぷり含めた食事を作ることができます。また、産地や鮮度などにこだわりが持てるのもメリットの一つ。愛犬の年齢や体重はもちろん、体調の変化に合わせて調理ができます。さらに、食材をそのまま調理するため色彩も良く、素材の味を活かせるでしょう。
一方で、以下のようなデメリットがあるため注意が必要です。
・栄養のバランスが取れた食事を作るのが難しい
・食材の加工・調理などに時間や手間がかかる
・保存がきかない など
総合栄養食並みの栄養のバランスが取れた手作り食を作るには、ペット栄養学や調理学などの専門知識が必要です。また、加工や調理に時間や手間がかかる上に、保存がききません。
手作りのコツ
犬のご飯を手作りする場合、下記のポイントを覚えておくと良いでしょう。
・鶏のササミをメイン食材にする
・イモ類を使用する
・食物繊維を多く取りすぎないように注意する
・市販の良質なドッグフードや療法食を合わせる
鶏のササミは肉類の中でも脂肪が少なく、消化しやすい良質なタンパク質を含んでいます。鶏のササミを中心にメニューを考えれば、膵炎の治療中の食事に必要な「低脂肪」と「良質なタンパク質」の条件が満たせます。
イモ類はエネルギー源として利用でき、血糖値が緩やかに上昇するため、糖尿病を合併した犬の食事におすすめです。ただし、食物繊維が多くなりすぎると消化不良を起こす可能性があるため、注意しましょう。
また、手作り食だけでは栄養のバランスが偏る可能性があるので、市販の良質なドッグフードや、動物病院などで手に入る療法食と合わせて与えるのがおすすめです。
犬が膵炎になった場合の食事のポイント

膵炎にかかると、みるみるうちに食欲が低下する犬も少なくありません。食欲がない、もしくはご飯が食べづらそうと感じた場合は、水分を足したり食事を温めたりしてあげると良いでしょう。
水分を足してあげる
膵炎を治療している間の食事は、水分を足して、ほぐしたりふやかしたりしてから与えるようにしましょう。水分を足すのはドライタイプのドッグフードだけでなく、手作り食も同様です。
食事に水分を足してあげると、ご飯が食べやすくなります。また、水分を吸って食材がやわらかくなると消化しやすくなるため、膵臓や腸への負担を減らすことができます。同時に水分も一緒に摂れるため、脱水の予防ができます。
犬の食事を手作りするなら、余熱を冷ました食材のゆで汁や煮汁をご飯と一緒にお皿に入れてあげると良いでしょう。
食事を温めてあげる
犬の食欲が低下している場合は、食事を温めてから与えるのがおすすめです。食事を温めることで、ドッグフードや食材の香りが強くなり、犬の食欲が刺激される可能性があります。また、温かい食事は口当たりが良く、犬は体温に近い温度の食べ物を好む傾向があることも覚えておきましょう。
ただし、梅雨の時期や夏の場合、ふやかしたドッグフードや手作りの食材は痛みやすくなるので、食べ残しがある場合は放置せずなるべく早く片付けることが大切です。また、嘔吐などの症状が出ている場合は、香りが強くなると吐き気が悪化することがあるため注意しましょう。
まとめ
犬が膵炎になった場合、低脂肪や消化の良さなどを考慮した食事管理が必要です。治療中は、アミノ酸のバランスが取れた良質なタンパク質など、体が必要としている栄養素をしっかり含んだ食事を与えるようにしましょう。
食事にはドッグフードと手作りの2つの選択肢がありますが、ドッグフードを検討している場合、どのフードが良いのか迷ってしまうことがあると思います。そのような人におすすめなのが、わんちゃんライフの「タミ―レシピ」です。
タミーレシピは、低脂肪で良質な脂肪・タンパク質や食物繊維を含む食材を使用した、手作りご飯です。ペットの食育指導士と獣医師が共同で監修しているなどの特徴もあり、味や見た目も工夫されています。愛犬の膵炎にぴったりな食事を探している人は、ぜひお試しください。
わんちゃんライフについて
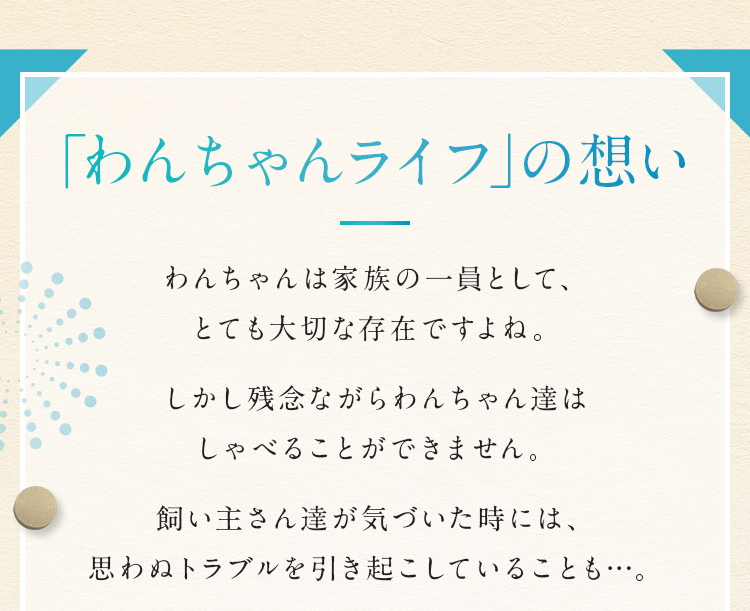
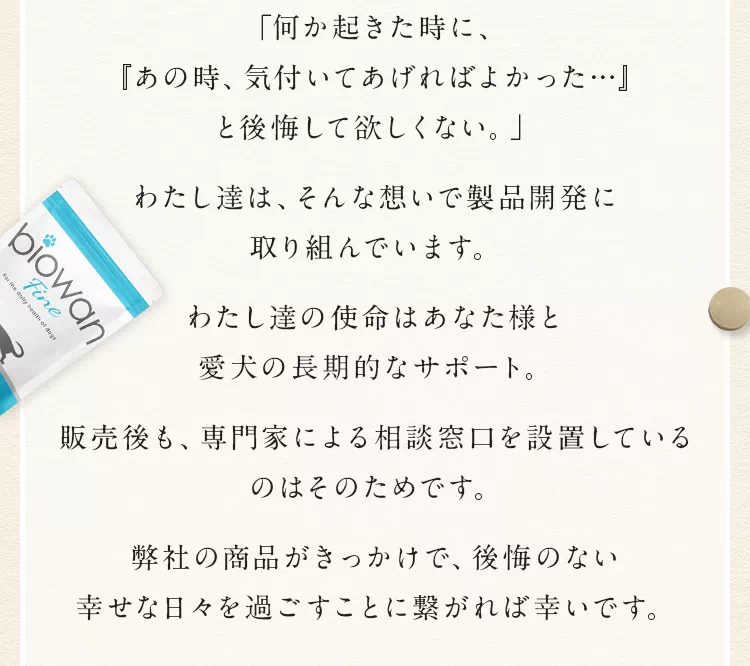


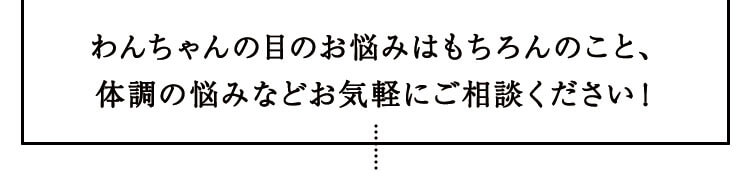

「わんちゃんライフ」では、HPよりドックフード・日用品・サプリメントなどの商品をお得に購入することができます。
500円OFFクーポンを公式ラインから取得し、ぜひご活用ください。
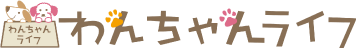



 ログイン
ログイン
 カート
カート
 お問い合わせ
お問い合わせ
 商品ラインナップ
商品ラインナップ
 カート
カート
 お問い合わせ
お問い合わせ
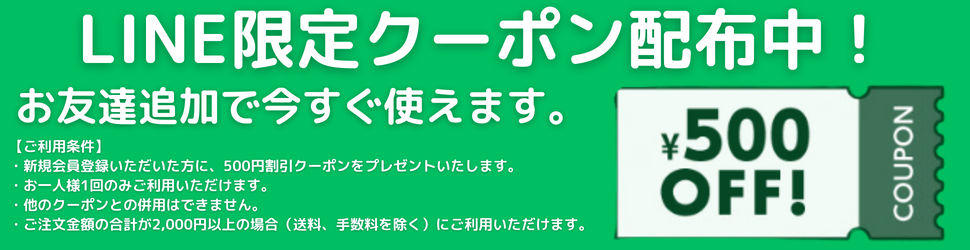
 ラインナップはこちらから
ラインナップはこちらから お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら