犬の尿路結石の症状は?原因と予防について

排尿量が増えたり頻尿になったりと様々な症状が現れる犬の尿路結石(尿石症)。再発を繰り返す病気でもあるため、しっかりとケアをしていくことが大切になってきます。 今回は犬の尿路結石症について症状や原因、予防法や治療法などについて詳しく解説していきます。
犬の尿路結石とは?どんな病気?
尿路結石症とは尿石症とも呼ばれる病気で、発症すると腎臓や尿管、膀胱、尿道などの尿路系に結石を形成し炎症や閉塞の原因になってしまいます。
尿路結石症の症状は、結石が形成された部位により異なります。
診断には問診や症状の確認と合わせて、以下のような検査を行うことがあります。
レントゲン検査、エコー検査 レントゲン検査やエコー検査により、尿路結石の有無を確認することができます。
治療は大きく内科療法と外科療法に分けられます。
尿石について
尿石は、尿に含まれるさまざまなミネラル成分が結晶化し、腎臓、膀胱、尿道などの泌尿器で結石となり、さまざまな症状を引き起こす病気です。
尿石ができるのには、食事や排泄環境が大きく関与しますが、根本的な原因は体質になります。
どんな症状?
尿路結石症の症状は、結石が形成された部位により異なります。
特に症状を示さないことも多いですが、血尿や痛みなどの症状を示すこともあります。
結石が細かい砂状の場合は症状を示さないこともあります。
初期症状について
膀胱の炎症が強い場合は、残尿感がひどくなるため、いつもトイレを失敗しないペットがあちこちに粗相してしまう、あるいは何度もトイレに行く、という行動の変化も見られます。
症状が悪化すると…?
尿道閉塞により排尿できなくなると、ぐったりして元気がない、嘔吐するなどの症状が現れ、ひどい時には急性腎不全に陥ってしまうこともあります。
この場合は早急な治療が必要です。
尿石と診断されたことがある場合は、膀胱炎の症状が出てしまったらすぐ治療を受けるようにしましょう。
原因は?
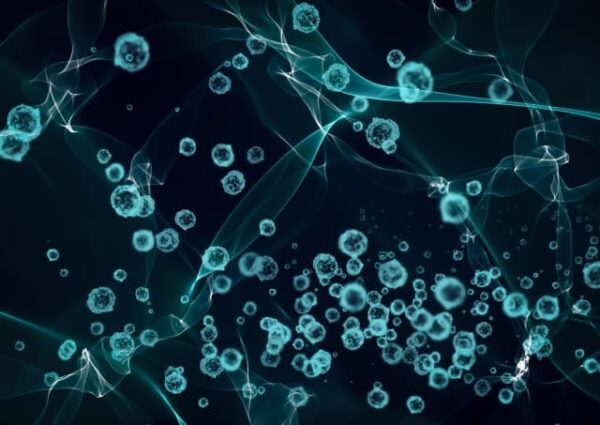
結石の種類 いくつかありますが、犬ではストルバイト(リン酸アンモニウムマグネシウム)、シュウ酸カルシウム、尿酸アンモニウムなどが多く見られます。
これら結石の種類により原因が若干違ってきます。
原因 1:細菌感染(細菌が感染してPHが変化したり、結石の発生要因となります)
2:不適切な食餌やおやつ(結石の成分である、ある種のミネラルの過剰摂取)
3:尿のPH(結石結晶の種類により、酸性やアルカリ性になると析出してくる)
4:尿量や排尿回数 (尿量が少なければ尿は濃くなり結石・結晶はできやすくなる)
5:犬種(特定の犬種において 発生しやすい傾向がある)
膀胱炎
膀胱炎は、尿石によっても引き起こされますが、逆に尿石の原因ともなることもあります。
炎症により膀胱内で細菌が増えると、尿の酸性度がアルカリ性に傾きます。
特に女の子は尿道から膀胱までの距離が短いため、細菌感染による膀胱炎になりやすく、注意が必要です。
食事の影響
ミネラル分の多い食べ物や水、タンパク質の多い食事は、尿石ができやすくなります。
トイレの回数が少ない
「トイレの回数が少ない=膀胱に尿がたまる時間が長い」こととなります。
トイレの回数が減る原因としては、外でのみ排泄させている、トイレの場所が寒かったり暑かったりでトイレに行きたがらない、冬場などに飲水量自体が減る、運動不足で代謝によりできる水分が減る、などがあげられます。
尿石症になりやすい犬種は?

好発犬種は、ダルメシアン、ミニチュア・シュナウザー、ヨークシャー・テリア、シー・ズー、ラサアプソ、ブルドッグ、ダックスフンド、キャバリア・キング・チャールズ・スパニエルなどが挙げられます
犬種による尿路結石のタイプの差があり、シー・ズー、ミニチュア・シュナウザー、ヨークシャー・テリア(シュウ酸カルシウム、尿酸塩)、ダルメシアン(尿酸塩)、ブルドッグ(尿酸塩、シスチン)、ダックスフンド(シスチン)、キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル(キサンチン)の好発があります。
予防方法は?
基本的な予防としては、結石のできにくい体質にすることで、結石のできる原因のひとつである尿路感染症の予防をしつつ、こまめな水分補給や食事の回数を少量の複数回に変更する食事療法などが有効と言われています。
動物病院で定期的に飼い犬の尿検査をしてもらうことも予防につながります。
「ストルバイト尿路結石症」の場合

ストルバイト結石は、尿中のpHを中性(pH6~7)に保つことで溶かすことができます。
ストルバイト尿路結石症の症状
無症状である場合もありますが、結石ができることで粘膜に物理的刺激が発生し、炎症が起こり、頻尿・血尿、ひどい場合では発熱・ショックを引き起こす事もあります。
ストルバイト尿路結石症と細菌感染
感染した細菌は、尿素を加水分解してアンモニアと二酸化炭素を生成し、尿のpHを上昇させ、ストルバイトを生成します。(逆にpHが低下すれば、ストルバイトは溶けます)
ストルバイト尿石の多くは膀胱に発生しますが、犬の腎臓や尿管にも発生することがあります。
ストルバイト尿路結石症の治療
結石がまだ形成されていない場合は細菌感染の抑制、消炎剤の投薬などから始まり、慢性症例の場合は食事管理が必要になることもあります。
ストルバイトの食事について
小さいものだと療法食により結石溶解効果が見込めますが、溶解には長時間かかります。
ミネラル成分を調整した専用の療法食があるので、先生とよく相談していきましょう。
中には一般食やサプリメント、手作り食で管理されるご家族もいらっしゃいます。
「シュウ酸カルシウム」の場合
自然に体外に出てくるまで経過観察するか、外科手術によって摘出して尿石が新たにできないように療法食で維持していきます。
ストルバイトと同じように、ミネラルを調節してpHも調節してくれる専用の療法食があります。
石の種類が2つ以上ある場合
療法食で溶解・維持がむずかしいため外科的手術を行うことが多いでしょう。
もしなってしまったら…。治療法は?

治療は、外科的に結石を摘出するか、食事療法や内科療法が行われます。
犬によっては、食事管理のみで満足のいく治療が可能です。
場合により、なかなか治らなかったり、再発を繰り返すこともあり、一生処方食などの食餌管理が必要となることもあります。
完治が困難であったり、再発を繰り返す場合があります。
療法食以外は与えないように
治療として食事療法を取り入れる場合、かかりつけの動物病院で処方される療法食を使うことが推奨されます
療法食の効果を高めるためにも、療法食以外の食事やおやつは与えないようにしましょう。
お水を飲ませる工夫を
飲水量を増やすために、水の器の数を増やす・冬場は少し暖めて与えたり、夏場は氷を入れて冷たくするなど愛犬の好みに合わせるとよいでしょう。
トイレの回数を増やす
なるべく膀胱に尿を貯めさせないために、トイレの回数を増やすようにしましょう。
早めに動物病院で検査することが大切!

まず、膀胱炎など尿トラブルがあったら、早めにかかりつけの動物病院で尿検査をしてもらいましょう。
さいごに
家族である飼い主さんのほんの少しの心がけで予防することができる病気なので、適度な運動と水分補給を日頃から心がけてあげてください。
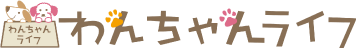



 ログイン
ログイン
 カート
カート
 お問い合わせ
お問い合わせ
 商品ラインナップ
商品ラインナップ
 カート
カート
 お問い合わせ
お問い合わせ
 ラインナップはこちらから
ラインナップはこちらから お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら