犬の心臓病の食事の与え方とは?【気をつけるポイントを解説】

愛犬が「心臓病」を患ってしまった場合、日常生活での体調管理がより大切になってきます。
適度な運動はもちろんですが、肥満にならないようバランスのとれた食事なども意識しなければなりません。その為、食事においても、どのようにコントロールすればいいのか考える飼い主さんも多いかもしれません。
今回は心臓病の犬の日々の食事の中で気をつけるべきことを解説していきます。
心臓病の犬が取り過ぎてはいけないものとは?
犬の心臓病と食事を考える上で大切なのは、ナトリウムの過剰摂取防止と適正体重の維持です。
とくに心臓病の症状が進むにつれて、ナトリウムの取り過ぎは注意しなければなりません。ナトリウムは体内に貯められると、心臓肥大や静脈のうっ血が進み、血圧が上昇します。
いわゆる塩分の取り過ぎなどで起こる症状です。とくに重度の疾患の場合は、ドッグフードを選ぶ際に、高ナトリウムのものは避けましょう。
ドライフードの目安
ドライフードにおいては、ナトリウム量が0.08~0.25であることを目安に選んでみましょう。
ただし初期状態と診断された場合は、さほど神経質になる必要はありません。
とくに犬は人よりもナトリウムを排出する能力が高いと言われています。そのため腎臓や他の臓器に問題がない場合、市販のドッグフードを食べて心臓状態が悪化するということは通常ないでしょう。
ただし、おやつを与えている場合は注意が必要です。おやつに含まれている塩分量が影響を与えてしまうケースがあるからです。
そのため、症状が軽い場合は、軽度にナトリウムを制限しながら、適正体重を維持した食事をとることが大切です。
ちなみに、心臓に加えて腎臓が悪くなっているときは、ナトリウムに加えてリンの制限も必要です。慢性腎臓病を起こす傾向があると言われているので注意が必要です。
心臓病の犬が積極的に摂取したいもの
一方、摂取しなければならないのが、「タウリン」です。
タウリンは、心臓や筋肉に多く含まれており、拡張型心筋症を患っている犬の場合は、心筋の中にあるタウリン濃度が低下していると言われています。
犬は体内でタウリンを合成することも可能ですが、犬種によっては十分に合成できない可能性もあるとも指摘されています。
タウリンを多量に摂取しても、毒性が出るということは言われておらず、直接タウリンを摂取させることも方法の一つです。
サプリメントなどをうまく活用し、上手にタウリンを取り入れましょう。またバランスがいいミネラルを含んだ食事も心がけるとよいでしょう。
とくに心臓病の投薬治療では、降圧利尿剤を投与している場合があります。これにより、尿中においてナトリウムやカリウム、ビタミンB群が失われる場合もあります。
ビタミンB群は、”代謝ビタミン”と言われ、様々な物質の代謝に大きく関与することが出来るのです。
小腸から吸収されたビタミンB群は、体内をめぐってすべての細胞に渡るエネルギーを効率よく変換・供給するために作用します。
心臓病の犬が摂取すべき食事とは?

食材としてあげられるのが、豚肉やレバー、カツオやサンマなどの肉や魚です。
また牛乳やバナナ、ナッツなどにも多く含まれています。
これらの食材には、カリウムや適度な量のナトリウムも含まれています。
一日の栄養摂取バランスを考えるうえでも、是非意識しておきたいポイントです。
手作りのドッグフードの活用も有効!
手作りの食事を与える方法もあります。
年齢や体重、アレルギーなど自分の犬にあった食事を与えることができるほか、添加物や保存料を使う必要もありません。
また生食をあたえることによって、酵素を摂取できるというメリットもあります。
ただし手作りの場合、特に食材バランスに気を配ることが大切です。
「肉と魚」「野菜」「穀類」のバランスを、年齢や体質、運動量に合わせて調整しながら与えなければなりません。
また補助的な役割として、サプリメントを一緒に取り入れることで、より効率的に栄養バランスを整えることができます。
まとめ

心臓病であっても、食事を考える上で大切なのは、愛犬が美味しく楽しく食べられるということです。
もちろん過剰に与えることはよくありませんが、神経質になりすぎると、飼い主さんも愛犬もストレスになってしまいます。
適度な運動や定期健診なども併せて行いながら、心臓病とうまく付き合っていきましょう。
わんちゃんライフについて
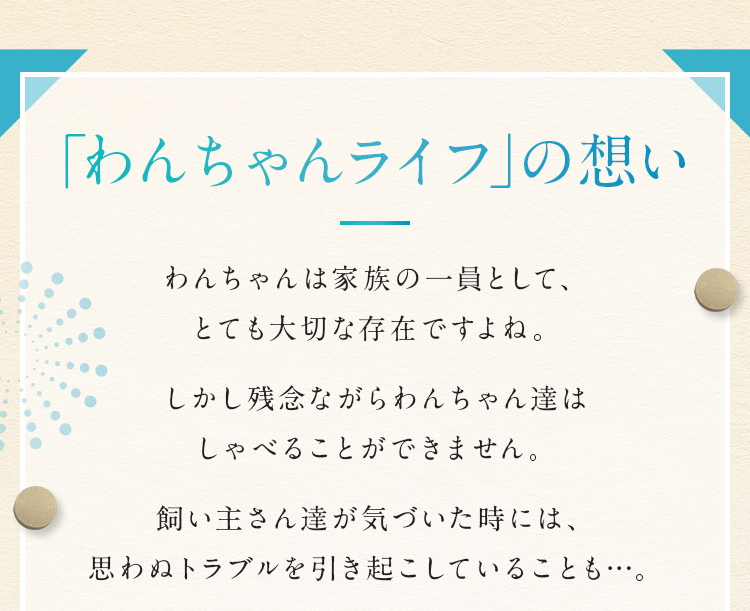
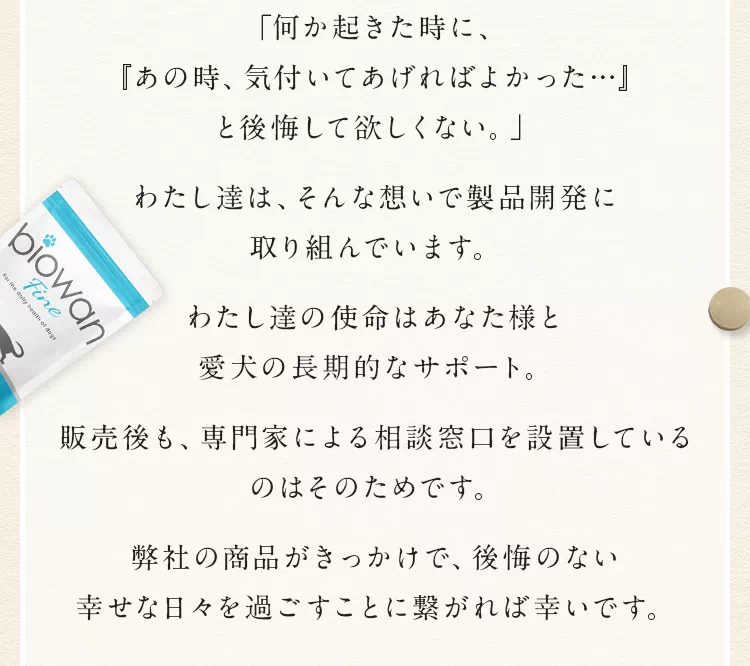


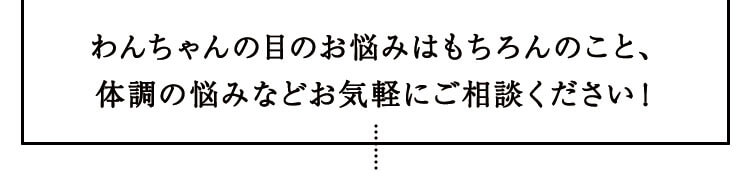

「わんちゃんライフ」では、HPよりドックフード・日用品・サプリメントなどの商品をお得に購入することができます。
500円OFFクーポンを公式ラインから取得し、ぜひご活用ください。
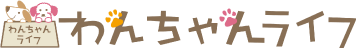



 ログイン
ログイン
 カート
カート
 お問い合わせ
お問い合わせ
 商品ラインナップ
商品ラインナップ
 カート
カート
 お問い合わせ
お問い合わせ
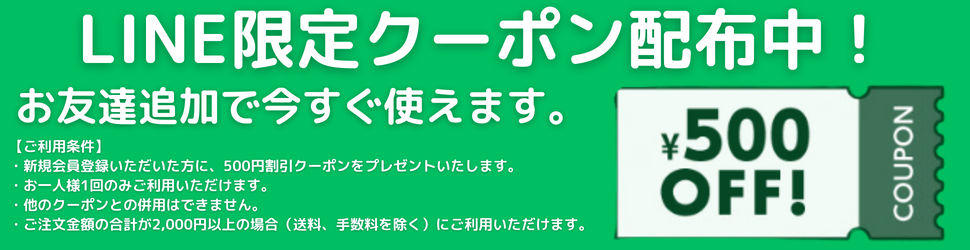
 ラインナップはこちらから
ラインナップはこちらから お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら